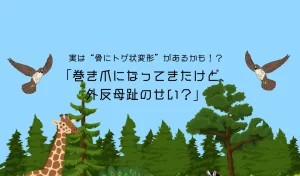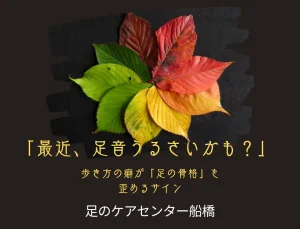第470歩「朝起きたら首が回らない…」それ、“足のせい”かもしれません【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】
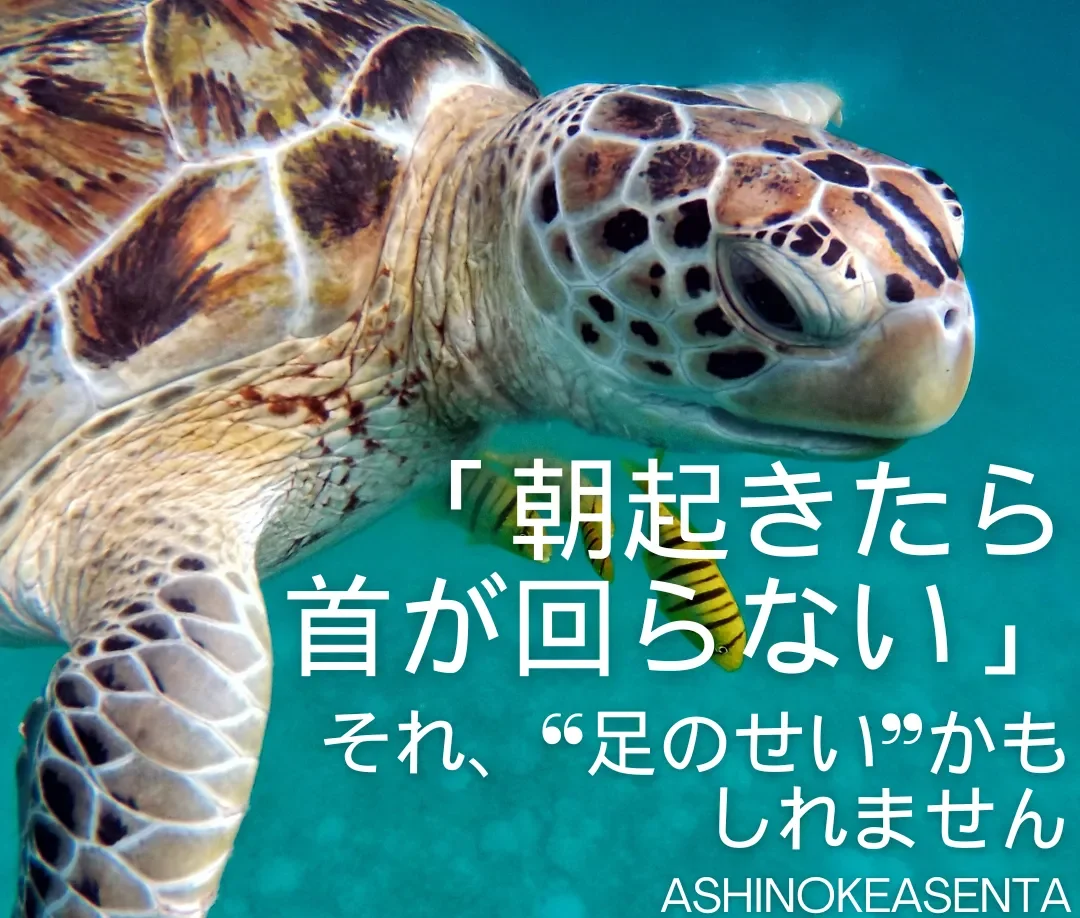
QFA:首の寝違えの本当の原因は「首」だけではない? 足元から見直す、冬の寝違え対策
Q. 寝違えって、ただの寝方の問題じゃないの?
A. 実は「首」だけの問題ではありません。
スマホやパソコンによる筋肉の硬さ、そして伸びない筋肉を長時間伸ばし続けて寝てしまったことも確かに要因ですが、足元の崩れ(重心の乱れ)が首への負担を増やし、寝違えを起こしやすくしていることも多いのです。
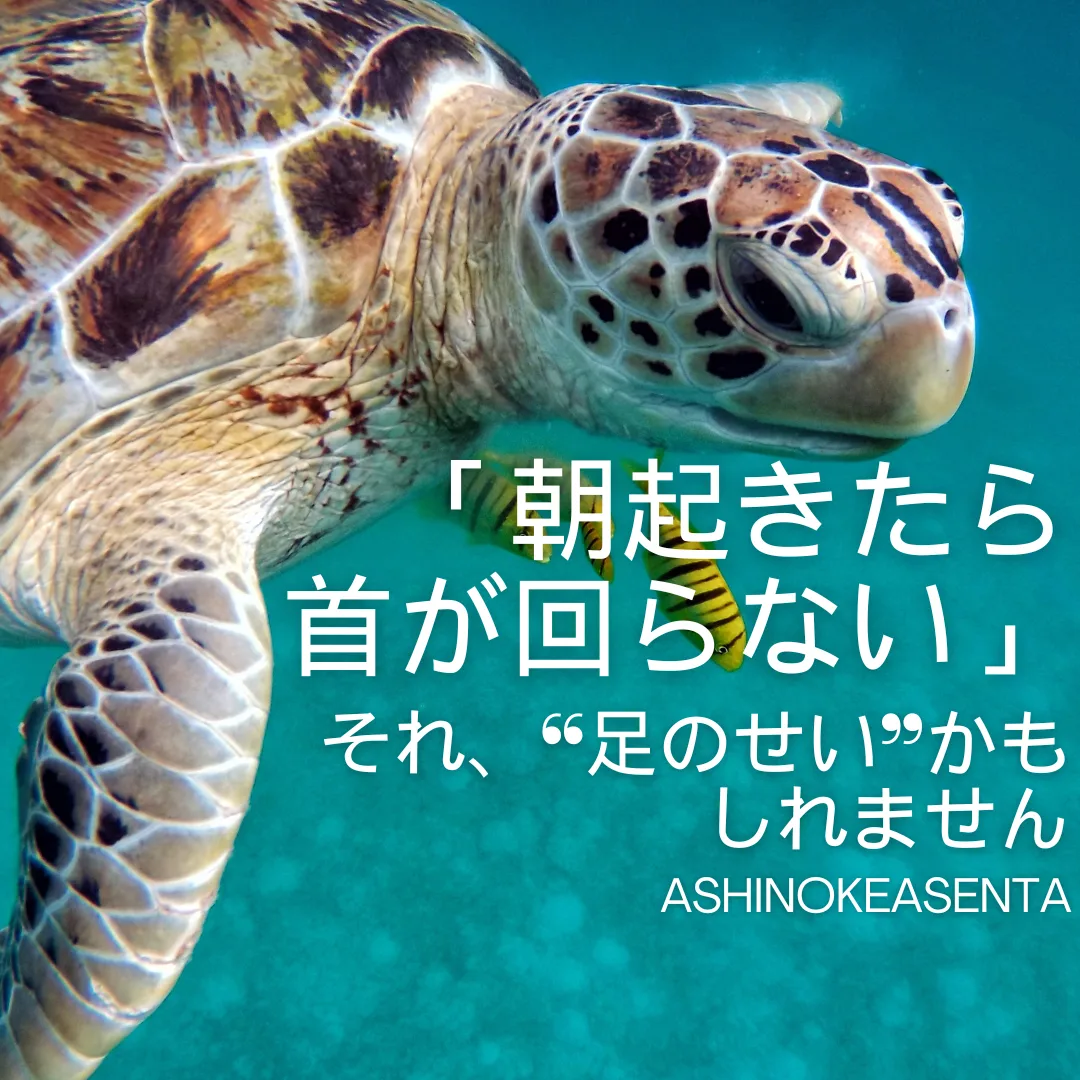
【概要】これから増える「首の寝違え」 寒さと疲労で起きやすい理由
寒くなる季節、「朝起きたら首が痛くて動かない…」という寝違えの相談が私達の業界では増えてきます。
一見、寝方や枕の問題に思われがちですが、実際には体のバランスの乱れが関係しています。
寒冷期や疲労時には、筋肉や靭帯の柔軟性が低下します。そんな状態で無理に首を伸ばした姿勢が続くと、睡眠中に筋肉が「軽い肉離れ状態」になることも。
これが、いわゆる寝違えです。傷病名は「頸部捻挫(けいぶねんざ)」です!
【なぜ?】首周りの筋肉・靭帯が硬くなる3つの要因
-
スマホ・PC姿勢の長時間化
→ 下を向く姿勢が続くことで、首の前側の筋肉が縮こまり、後ろ側が引き伸ばされ続ける。 -
寒さによる血流低下
→ 冷えで筋肉が硬くなり、回復力が落ちる。 -
足元の不安定さ(重心の崩れ)
→ 意外に見落とされがちですが、実はこれも全身のバランスを崩す大きな要因となります。
【重要】首の寝違えは「足」から始まっている?
大きなタワーを想像してみてください。
もし基礎(土台)が少しでも傾いたら、タワーの上部は大きく揺れますよね。
人の体も同じです。
足のアーチが崩れたり、重心が前後左右にズレたりすることで、全身のバランスが崩れます。
すると、最上部である「首」に過剰な力がかかり、知らぬ間に筋肉が緊張しっぱなしになります。
特に現代人は「前重心(つま先側に体が倒れる)」の人が多く、
その状態が続くと、首が常に頭を支えようとして引っ張られたままになります。
前重心ではない?いえいえ、実は体を正そうとすればするほど、皆様は胸を反らせてしまいます。すると足の前側に荷重がかかってしまうのです。正しい姿勢は、横からみて「外くるぶし→股関節→肩の骨→耳たぶ」までが一直線になります。
詳しくはこちら👉正しい姿勢の取り方を動画で説明しております
【チェックリスト】あなたの足・姿勢は大丈夫?
-
朝起きた時、首や肩がこり固まっている
-
スマホを見る時間が1日3時間以上
-
靴底の減り方が左右で違う
-
反り腰だ
-
土踏まずが低い、または足裏が疲れやすい
-
イスに座ると猫背になりやすい
→ 3つ以上当てはまる方は、「足元からくる首の負担」タイプかもしれません。
【専門家解説】理想の立ち方・姿勢で首を守る
足のケアセンター船橋では、「動作×足学×整体」を用いて、
足元から全身の姿勢バランスを整える指導を行っています。
正しい立ち方の基本は、
-
重心を「スネの真下」に置く
-
頭を「体の上に載せる」ようにする
たったこれだけで、首にかかる負担は大幅に減ります。
頸椎カラー(むち打ち時に使う首のサポーター)は、まさにこの「頭を体の上に乗せる」役割をしているのです。
つまり、正しい重心を身につければ自分の筋肉が支えとなり、寝違え予防率を上げることができるということです。
【セルフケア】寝違えを防ぐ3つのステップ
-
足の重心を整える
立つときに、かかとでもつま先でもなく「スネの下」に重心を置く。 -
姿勢をリセットする
スマホを見る前に一度「ミゾオチを後ろに引く」動作を。だいたい体がまっすぐになります。 -
入浴・温め習慣を
冷えは筋肉を硬くします。お風呂で温めるだけでも血流が改善し、寝違え予防になります。
【まとめ】寝違えは“首の問題”ではなく“体全体の警告”
寝違えは「姿勢と足の崩れが限界に達したサイン」。
首を揉むよりも、足元と姿勢の見直しが根本解決の近道です。
足のケアセンター船橋では、足の構造・動作のプロとして、
外反母趾や扁平足などのトラブルを通して、全身のバランスを再教育しています。
「また寝違えた…」という方こそ、
まず足元から姿勢を見直してみましょう。