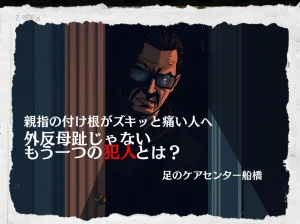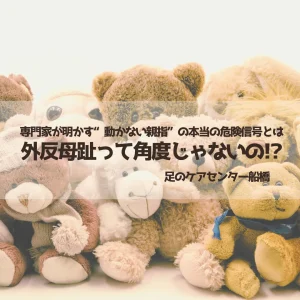第449歩「親指で踏ん張る派」vs「小指で支える派」体が安定するのはどっち?【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】

Q&A:親指で踏ん張るのはもう古い?体の安定には“足の外側”がカギ!
Q. 親指で踏ん張るのはなぜよくないの?正しい重心のかけ方は?
A. 親指に体重をかけすぎると、足が「回内(かいない)」という内側へのねじれを起こします。
これは足の骨格をゆるめ、土踏まずがつぶれ、全身のバランスを崩す原因になります。
結果として、腰・肩・首への負担や外反母趾・膝痛にもつながります。今、立って確認してみてください。もし、土踏まずを潰すように立っていれば、少しだけ「足の外側(小指側)」に重心を置いてみてください。外側を意識することで、足の骨格が引き締まり、体幹が安定しますよ!

力いっぱい小指側へ踏ん張ることはしなくて大丈夫です。少しだけ、小指側へ荷重をかけてあげてください。歩き出したら逆に意識しないようにしてください。日常の歩く前の立ち方を意識するだけで足の崩れを防ぐことができます。
自宅で「足の回内」をチェックする方法は?
スマホを使って簡単セルフチェックしてみましょう!
【足の回内チェックリスト】
☑ 立った状態で、内くるぶしが外くるぶしより地面に近い(内くるぶしが床方面へ下がっている)
☑ 土踏まずが低く、ペタンと平らに見える。もしくは実際に低い
☑ 立つと膝がまっすぐではない(O脚・X脚)
☑ 長時間立つと足裏や腰がだるくなる
上記のうち、2つ以上当てはまる場合は「足の回内(オーバープロネーション)」の可能性があります。
スマホをかかと側の床に置いて、後ろからセルフタイマーで撮影してみましょう!いつもは自分で見れない部分をみることができます!
親指重心が生む“ねじれの連鎖”
かつての運動指導では「親指で踏ん張れ!」が定番でした。
しかし、親指側(内側)に体重をかけると、足は当然、土踏まず側へ落ちていきます。ということは足首が内側に倒れます。膝も内側へ入り(人によっては外側へ)、骨盤も前傾し、上半身までゆがみます。
つまり、「親指重心」は足だけでなく全身のバランスを崩す原因になるのです。
【実験】どちらが安定する?親指 vs 小指
-
両足を肩幅に開き、サーフィンのような構えをとります。
-
親指側にグッと力を入れて立ち、誰かに横から軽く押してもらいましょう。
→ 意外と簡単にグラッとします。 -
次に、小指側(外側)に重心を移して同じように押してもらいます。
→ 体がブレにくく、安定感が増したはずです。
これは、外側重心によって足の骨格(特に距骨・踵骨・中足骨)が自然に締まり、アーチ構造が支え合うため。
人間の足は「外側で支え、内側でしなる」構造になっているのです。
「足の外側」を意識するだけで姿勢が変わる
「足の外側」=小指側ラインを意識することで、
・膝が真っすぐになる
・骨盤の傾きが整う
・わざわざ胸を張らずに、自然に姿勢が良くなる
といった効果が期待できます。
足のケアセンター船橋では、こうした「重心のかけ方」から体全体を見直すケアを行っています。
単なるマッサージではなく、「足学・動作・整体」の3方向からアプローチするため、
姿勢や歩き方そのものを改善できるのが特徴です。
まとめ:古い“親指神話”から抜け出そう
昭和の時代には「親指で踏ん張れ!」が正しいとされていました。
しかし今では、体の安定をつくるのは「外側ライン」であることが明らかになっています。
立っている時に親指重心をやめて外側を意識するだけで、
・土踏まずが自然に支えられる
・膝や腰の負担が減る
・姿勢が整う
そんな変化を実感する方が多いのです。
毎日の立ち方・歩き方を少し変えるだけで、体は驚くほど軽くなります。
あなたもぜひ、今日から“外側重心”を試してみてください。
それが、本当の「安定した体」を取り戻す第一歩です。
👣 専門監修:足のケアセンター船橋 髙野篤史
👣 参考:足育研究会(https://www.sokuiku.jp/)