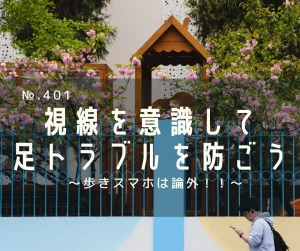第402歩 足の痛みの黒幕は“土踏まず”だった!今すぐ要チェック!【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】
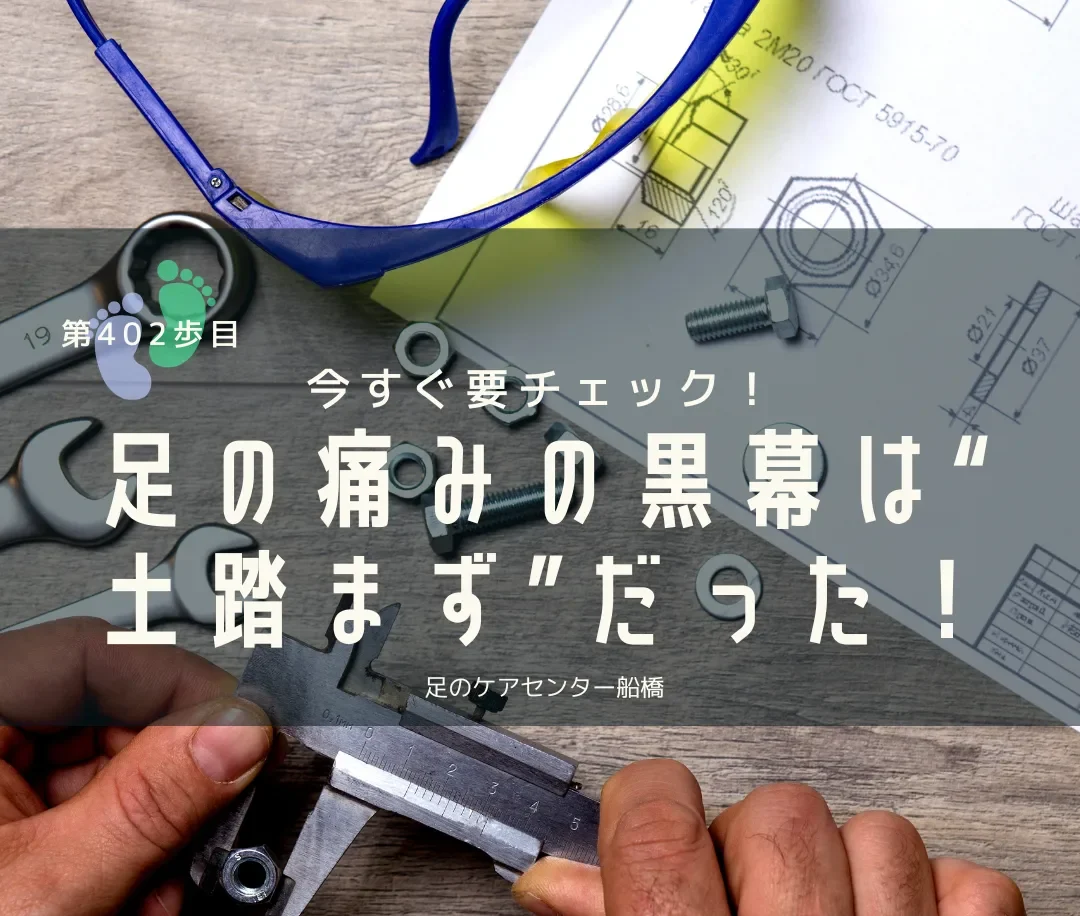
「いつの間に…?」土踏まずの“低さ”に気づいたあなたへ
あなたがふと「土踏まずが低いかも?」と感じたことはありますか?実はその気づき、とても大切なサインです。土踏まずは足の裏にあるアーチ構造で、歩くときや走るときに体へかかる衝撃をやわらげる役割を果たしています。
人は歩くだけで体重の約3倍、走ると5倍もの負荷が足にかかると言われています。その衝撃を吸収してくれるのが土踏まずです。しかし、この部分が低くなってくるとクッション機能が失われ、膝や股関節、腰、そして首にまで衝撃が伝わりやすくなってしまいます。その結果、「足が疲れやすい」「腰がだるい」「姿勢が崩れてきた」など、日常生活の中で不調を感じやすくなるのです。
土踏まずが低くなると何が起きる?
土踏まずが低下すると、足幅が広がりやすくなります。これを「開帳足」と呼びます。開帳足は靴に足が当たりやすくなるため、タコや魚の目ができたり、親指の付け根が外に出っ張る外反母趾や、小指側が内側に入り込む内反小趾といった足の変形につながることもあります。
日本人は欧米人に比べて足の甲が薄く、もともと土踏まずも低め。だからこそ扁平足や足の崩れが起こりやすい体質だといえます。足は身体の土台。その土台が崩れることで、健康寿命が短くなってしまうリスクもあるのです。
あなたの足をセルフチェック
「もしかして自分も?」と思った方は、ぜひ簡単なセルフチェックをしてみましょう。
-
座って足の裏を合わせたとき、土踏まずにしっかりとしたくぼみがあるか
-
立った状態で足の内側に定規を当てたとき、土踏まずに2~3cmの高さがあるか(出来れば第三者にみてもらいましょう)
隙間が1cm未満しかなかったり、土踏まずがつぶれてしまっているように見える場合は、アーチが低下しているサインかもしれません。
土踏まずを守るための習慣
1. 重心を意識する
立っているときに、スネの下あたりに重心を置くイメージをしてみましょう。歩いているときよりも、立ち止まっているときに意識するのが効果的です。わかりずらければ、足の小指側に重心を持っていきましょう。
2. 靴やインソールを見直す
足に合っていない靴は、土踏まずの崩れを助長します。縦のサイズだけでなく横幅も合った靴を選ぶことが大切です。柔らかすぎる靴よりも、しっかり足を支えてくれるものがおすすめです。
3. 骨寄せ運動をする
足の指を地面に押し当てるように力を入れ、そのときに土踏まずが持ち上がるのを意識しましょう。単純なグーパー運動よりも、アーチを保つための筋肉を鍛えることができます。👉こちらが骨寄せ運動です。朝晩10回づつくやってみてください。
4. 専門家に相談する
セルフケアで改善が難しい場合は、足の専門施設や整体院でチェックしてもらうことも大切です。自分では気づけない足の癖や歩き方を知ることで、予防につながります。
まとめ
土踏まずは、あなたの身体を守る大切なクッション。低下すると足だけでなく、全身の不調につながります。日常生活の中で少し意識するだけでも、アーチは守ることができます。
もし最近「足が疲れやすい」「靴が合わなくなってきた」と感じるなら、それは土踏まずからのSOSかもしれません。今日からできる小さな習慣で、未来の健康寿命を守っていきましょう。