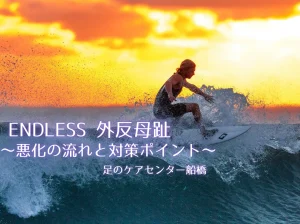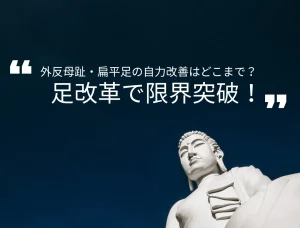第386歩 足にやさしい階段の上り方!外反母趾やタコを防ぐ足育メソッド【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】
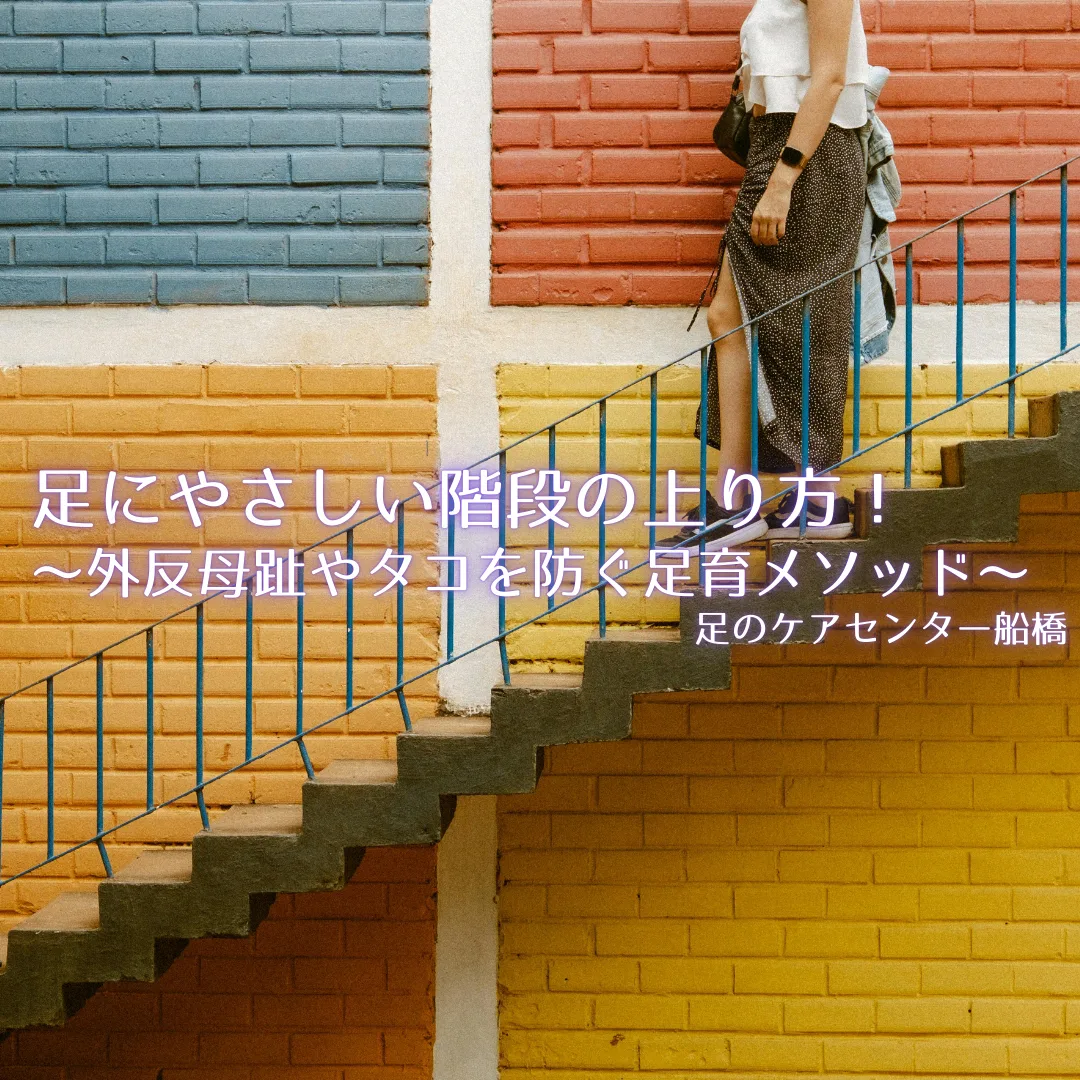
階段の上り方・下り方で変わる!外反母趾・タコ・膝痛を予防する正しい体の使い方
「階段を上ると足先が痛い」「タコや魚の目がなかなか治らない」「膝への負担が気になる」
そんなお悩みは、もしかすると階段の上り方・下り方のクセが原因かもしれません。
この記事では、外反母趾や足のトラブル、膝痛を防ぐための正しい階段の使い方を、足育(そくいく)の視点から詳しく解説します。
間違った階段の上り方が招く足と膝のトラブル
前足で踏み込む動きが危険な理由
多くの方は、階段を上るときに段の先端へ前足を置き、グッと踏み込む動きをしています。
この動きは足の前側にほぼ100%の体重をかけてしまい、以下のトラブルを引き起こします。
-
足幅が広がり、親指が内側に押され外反母趾が進行
-
第2趾の付け根に圧力が集中し、タコや魚の目が悪化
-
膝関節に体重の約5倍の負荷がかかる
ヒール・パンプス愛用者は特に注意
女性に多いのが、ヒールやパンプスなど、かかとが浮いた状態でつま先だけを段に乗せて上る動作。
これは足指や中足部に強いストレスをかけ、結果的に変形や慢性的な痛みにつながります。
正しい階段の上り方のポイント
後ろ足を引き上げる意識を持つ
足や膝を守る階段の上り方は、前足で踏ん張らず後ろ足を腹筋(腸腰筋)で引き上げることです。
-
後ろ足に意識を置く
-
お腹の奥にある腸腰筋を使って後ろ足を次の段に引き上げる
-
前足は「支え」として使い、過剰な踏み込みを避ける
腸腰筋は体の中心を貫く大きな筋肉で、脚の引き上げに適しています。
この筋肉を活用すれば、少ない力でスムーズに段を上り、足や膝への負担を大幅に減らせます。
体重の乗せ方を感じ取る
試しに「前足で踏み込む」場合は前:後=9:1くらいで体重が偏ります。「後ろ足を引き上げる」場合ですと前:後=4:6くらいになるでしょう。それによって足のアーチが崩れにくくなります。つまりこれは外反母趾など足のお悩みの進行予防にも直結します。
階段の下り方で衝撃を逃がす
衝撃をバネで分散させる
階段を下りるとき、着地の衝撃は足・膝・腰と全身に直接伝わります。
これを防ぐには、以下の主に3関節を軽く曲げて衝撃を逃がすことが重要です。
-
足首
-
膝
-
股関節
コップの水をこぼさないイメージ
簡単な練習法として「水を満タンに入れたコップを持ち、こぼさないように下りる」方法があります。
この動作により、自然に重心が安定し、衝撃を吸収する下り方が身につきます。
階段を日常の足育トレーニングに
正しい階段の上り下りは、足や膝の負担軽減だけでなく、腸腰筋や体幹の強化にもつながります。
足育(そくいく)の観点からも、階段は足のアーチ機能の維持・改善に効果的です。
毎日の移動をトレーニングに変えられる、最高の機会といえるでしょう。
まとめ:今日からできる階段の健康習慣
-
上りは後ろ足を腸腰筋で引き上げ、前足で踏ん張らない
-
下りは足首・膝・股関節をバネにして衝撃を逃がす
-
コップの水をこぼさないように歩くと自然に正しいフォームになる
階段は、正しい方法で使えば足・膝・腰を守る最高の味方です。今日から意識して、外反母趾・タコ・膝痛を予防しましょう。