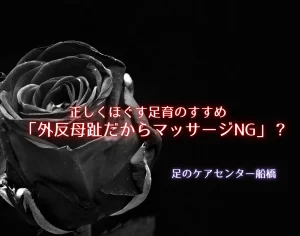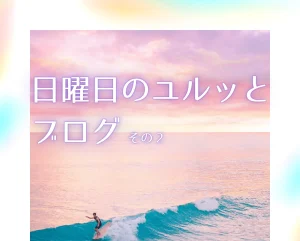第381歩 あっち痛いこっち痛いは開張足の仕業かも!?【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】

皆さんこの記事読まないだろうなー。でも読んで欲しいなーと思っています。なぜなら開帳足自体は自覚がない症状なので、開帳足と聞いてもピンときません。でも外反母趾・扁平足・タコ・魚の目・腰の痛み・肩のコリがある方は、ほぼ開帳足ですよ。土台が崩れたら、当然その上も・・・。ぜひお読みください!
自宅でできる!あなたの足は大丈夫?開張足セルフチェックと改善法
「最近、足の幅が広くなった気がする…」
「お気に入りの靴がきつく感じる」
そんな経験、ありませんか?
もしかすると、それは 開張足(かいちょうそく) のサインかもしれません。
開張足とは?
開張足は、足の横方向にある「横アーチ」が崩れ、指の付け根部分が横に広がってしまった状態です。
本来、足には縦のアーチ(土踏まず)と横のアーチがあり、この2つが歩行や立位の衝撃を吸収し、体を支えています。
ところが、横アーチが崩れると、足の幅が広がり、タコや魚の目、外反母趾、内反小趾などの変形が進みやすくなります。
自宅でできる!開張足セルフチェック
方法はとても簡単です。
-
椅子に座って、足を床から浮かせる
-
足の一番幅が広い部分をメジャーで一周測る
-
次に、立って体重をかけた状態で同じ場所を測る(他の人に計ってもらいましょう)
-
その差が 2.5cm以上 あれば、開張足の可能性大
この差は、横アーチがつぶれて足幅が広がっている証拠です。
さらに指先が地面をしっかりつかめない「浮き指」がある場合も要注意です。
なぜ開張足になるの?
-
長時間の立ち仕事や歩き方の癖
-
サイズの合わない靴(特に大きめサイズ)を履き続ける
-
足の指や足裏の筋肉の衰え
-
ヒールやパンプスなど、つま先に負担がかかる靴の習慣
こうした要因で骨同士の間隔が広がり、横アーチが崩れてしまいます。
足育(足の正しい使い方や筋力維持の習慣)を取り入れない限り、自然に元通りになることは難しいのです。
開張足が体に与える影響
開張足になると、土踏まずの機能が低下し、衝撃吸収がうまくできなくなります。
その結果、足だけでなく膝・腰・首などにも負担がかかり、慢性的な痛みや姿勢の崩れにつながることも。
また、足の幅が広がることで靴選びが難しくなり、ますます足に合わない靴を履く悪循環に陥ります。
改善の第一歩は「靴選び」
多くの方が立ったときの足幅で靴を選びますが、この状態では足が広がっているため、大きめサイズを選びがち。
結果として、靴の中で足が動きすぎ、タコや魚の目、外反母趾を悪化させてしまいます。
正しい靴選びのポイントは、体重をかけていないときの足幅で合わせること。
最初は少しきつく感じても、それ以上広がるのを防ぐことができます。
足育で予防・改善
-
立っている時はスネの下に重心を置く
-
スネの下に重心を置いてから、歩き始める(歩き始めたら重心は気にせずでOK)
- 骨寄せ運動を行う👉足指を地面に接地させて、地面を踏みしめるようにします
- インソールを活用する
足元を見直すことは、将来の健康寿命を延ばす大切な投資です。
まずはセルフチェックで現状を知り、正しい靴と足の使い方を取り入れてみましょう。