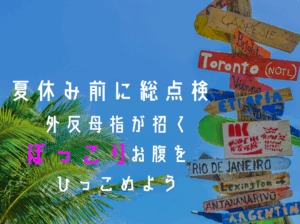第357歩 セーバー病「かかとが痛い」は成長のサイン?正しい足の使い方を学ぼう【外反母趾.足育をはじめとした足の悩みの整体院 西船橋1分】

「うちの子、かかとが痛いって言ってる…」もしかしてセーバー病かも?
「ねぇママ、かかとが痛い…」「パパ、練習中にかかとがジンジンするんだよ」
お子さんがそんな言葉を口にしたら、もしかしたらそれはセーバー病かもしれません。特に、活発な10歳前後の男の子に多く見られるこの痛み。わが子が痛みを訴えると、親としては心配でたまりませんよね。
「このまま運動を続けても大丈夫なの?」「どうしたら早く良くなるんだろう?」
そんなお父さん、お母さんの不安を解消するために、今回はセーバー病の正体から、家庭でできるケア、そして当センターが推奨する具体的な改善策まで、詳しくお話しします。
そのかかとの痛み、放置しないで!「セーバー病」って何?
セーバー病は、正式名称を「踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう)」と言い、成長期のお子さん特有のかかとの痛みです。お子さんの骨は、まだ大人とは少し違います。骨の端っこには「骨端核(こったんかく)」と呼ばれる、まるで「離れ小島」のような軟骨部分があります。この骨端核が成長とともに徐々に骨化し、やがて「本島」であるメインの骨と一体化していきます。
かかとのアキレス腱が付着する部分にも、この「離れ小島」があります。活発な運動、特にジャンプやダッシュなど、アキレス腱に強い負荷がかかる動きを繰り返すと、この「離れ小島」がアキレス腱に強く引っ張られてしまいます。
柔らかい「離れ小島」が強い力で何度も引っ張られることで、そこに炎症が起きたり、血流が悪くなったりして、痛みに繋がるのです。これがセーバー病の正体です。
なぜ10歳前後が多いのか? この時期は、骨が急速に成長する一方で、アキレス腱などの筋肉や腱の成長(発達)に骨の成長が追いつかないことが多く、バランスが崩れやすい時期だからです。さらに、サッカーや野球、バスケットボールなど、ふくらはぎに負担がかかりやすいスポーツに熱中するお子さんが多いため、発症しやすいと言われています。
セーバー病の「一般的な」対処法、そして意外な落とし穴
セーバー病の一般的な対処法としては、以下のようなものが挙げられます。
- インソールの使用: かかとへの衝撃を和らげる目的で、クッション性のあるインソールを使用します。
- 運動量の制限・中止: 痛みが強い場合は、一時的に運動を休止したり、量を減らしたりします。
- ストレッチ: アキレス腱やふくらはぎの筋肉を柔らかくすることで、負担を軽減します。
もちろん、これらの対処法も大切です。しかし、セーバー病は一度発症すると、痛みが完全に引くまで1年近くかかることも珍しくありません。
そして、ここで一つ注意点があります。 「かかとが痛いから、つま先に体重をかけて歩くようにしよう」と指導されるケースもありますが、実はこれが逆効果になることもあるんです。つま先に体重をかけると、足の前側に負担が集中し、土踏まずが潰れるような形になります。その結果、足の骨同士が開いてしまい、ふくらはぎの筋肉が引き伸ばされて、かえってアキレス腱が「離れ小島」を引っ張る力が強まってしまう可能性があるからです。
お子さんの成長を止めずに、痛みを和らげながらスポーツを続けさせてあげたい。そんな親御さんの願いを叶えるために、皆様にはもう少し別アプローチもご提案します。
お子さんの足を守る!今日からできる「重心」と「歩き方」の改善
当センターが提唱するのは、「足育」の考え方に基づいた根本的な改善です。足は体の土台であり、重心の位置や歩き方が全身に大きな影響を与えます。特に成長期のお子さんの足は、まだ未完成な部分が多く、正しい使い方を身につけることが非常に重要です。
1.「重心」を意識するだけで変わる!
お子さんがかかとの痛みを訴えると、無意識のうちにかかとを庇って、重心が前に偏りがちになります。しかし、セーバー病の痛みの原因は、かかとの「後ろ側」、つまりアキレス腱が付着している「離れ小島」の部分です。地面に接する部分だけではありません。
そこで意識してほしいのが、「重心をスネの真下」に置くことです。
この姿勢を意識するだけで、足の骨がキュッと締まり、土踏まずが立体的なアーチを保ちやすくなります。扁平足がちなお子さんにも効果が期待できますよ。そして、重心がスネの真下にくることで、ふくらはぎの筋肉もリラックスした状態になり、アキレス腱が「離れ小島」を引っ張る力が弱まるんです。
さらに効果を高めるために、痛みが強い時は、かかとの後ろ側(「離れ小島」のある部分)を軽く圧迫するようにテーピングするのもおすすめです。これは、不安定な「離れ小島」を物理的にサポートし、余計な引っ張りから守る目的があります。そして、靴の選び方と履き方も非常に重要です。お子さんの足に合った正しいサイズの靴を選び、かかとをしっかり合わせて(履いたら地面にカカトをトントン)紐やマジックテープで固定(一番上をしっかり留めます)しましょう。靴の中で足が動いてしまうと、かえって負担が増えてしまいます。
2.「行進」を意識して歩いてみよう!
次に大切なのが、歩き方です。 セーバー病のお子さんには「行進するように脚を上げて歩く」ことを試してみてください。
通常、歩くときにはかかとから着地し、つま先に重心が移動していきますが、この動作の中でアキレス腱は常に伸縮し、かかとの「離れ小島」に負担をかけています。しかし、行進のように脚を少し高く上げることで、足全体で地面に着地するような感覚になり、アキレス腱が急激に引っ張られる動きが軽減されます。
これによってアキレス腱への負担が減り、痛みの原因を根本から減らすことができるのです。日常生活の中で意識して取り入れるだけで、お子さんの足への負担が大きく変わるはずです。
セーバー病だけじゃない!「足裏の痛み」にも共通するケア
今回ご紹介した重心の位置や歩き方は、セーバー病だけでなく、成長期のお子さんによく見られる他の足のトラブルにも応用できます。
例えば、12歳から18歳くらいの女性に多く見られる「フライバーグ病」。これは足の指の付け根あたり、特に人差し指や中指の付け根部分の骨が痛む症状です。このような場合も、セーバー病と同様に靴のかかと側に足をしっかりセットし、行進するように歩くことを意識してみてください。足の指への過度な負担が減ることで、症状の改善が期待できます。
お子さんの足のトラブルは、その子の成長や運動能力にも大きく関わってきます。「たかが足の痛み」と軽視せず、早い段階で適切なケアをしてあげることが大切です。
まとめ:お子さんの未来の足を育てるために
お子さんの「かかとが痛い」というサインは、体からのSOSです。一時的な痛み止めでごまかすのではなく、根本的な原因に目を向け、足の使い方を見直すことが、お子さんの健やかな成長に繋がります。
当センターでは、お子さんの足の成長に特化した「キッズコース」もご用意しています。お子様一人ひとりの足の状態や歩き方を詳しく分析し、専門的なアドバイスとサポートを行っています。しかし、「うちの子は、そんな立ち方や歩き方など言う事聞くかな・・・」「無理だろ・・・」という場合は、適切なインソールを入れてあげるのが手っ取り早いです。そんな時もご相談ください。
もし、お子さんの足の痛みでお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。私たちと一緒に、お子さんの健やかな足と未来を育んでいきましょう。
Q&A:
Q: セーバー病の改善のために、特に意識すべき重心の位置と歩き方はありますか?
A: はい、あります。セーバー病の改善には、重心をスネの真下に置くことを意識しましょう。かかとが痛いからといって前に重心を逃がしがちですが、それは逆効果になる可能性があります。スネの真下に重心を置くことで、足の骨が締まり、ふくらはぎの筋肉も緩むため、アキレス腱が「離れ小島」を引っ張る力が弱まります。
また、歩き方としては、行進するように脚を上げて歩くことをおすすめします。これにより、アキレス腱が「離れ小島」を引っ張る力が弱まり、痛みの原因を減らすことができます。痛みが強い場合は、テーピングでかかとの後ろ側を圧迫したり、正しいサイズの靴をかかと側でしっかり固定して履くことも有効です。もしお子さんが正しい立ち方や歩き方を実践するのが難しい場合は、適切なインソールの使用も効果的な選択肢となりますので、ご相談ください。
ご自身の姿勢や足について知りたいな・・・という方はぜひ千葉県船橋市の当センターへいらしてください。外反母趾・内反小趾・たこ・ウオノメなど足でお悩みの方は足専門のトライアルコース2,980円でお試しいただけます。お気軽にお問合せください。美しい歩行も、日々の意識と少しのトレーニングで身につけることができます。